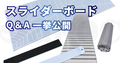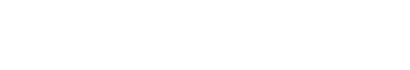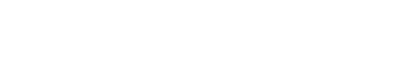高層ラック運用とピッキング効率の「ジレンマ」をハイピックランナーで解決!レンタルについても紹介!
物流センターでは「より多くの商品を」「より正確に」「より早く」入出荷するべく絶え間ない改善が求められています。しかし、ひとつひとつは良い改善でも、組み合わせ次第ではメリットが噛み合わず、全体の効率を下げてしまうことがあります。
この記事ではそんなケースのひとつとして、保管効率を上げるために導入した高層ラックが、商品を出荷する際のピッキング効率を下げてしまう現象の解説と、その解決策について紹介します。
目次[非表示]
- 1.EC市場の拡大と物流拠点の進化
- 2.物流センターの「ピッキング効率と保管効率のジレンマ」
- 3.高層ラック環境におけるピッキング効率改善方法
- 3.1.頻度分析による入庫位置調整
- 3.2.脚立や梯子の利用
- 3.3.高所作業車「ハイピックランナー®」の導入
- 3.3.1.ハイピックランナーでピッキングする場合の操作手順
- 3.4.自動倉庫
- 4.価格と安全面で考えれば「ハイピックランナー®」レンタルがおすすめ
- 4.1.メリット①初期費用が0円
- 4.2.メリット②高い安全性
- 4.3.メリット③ラックと合わせてレンタルも可能
- 5.まとめ
EC市場の拡大と物流拠点の進化
インターネット普及により、EC市場は急速に拡大しました。
それに伴い、物流拠点は単に商品を保管する「倉庫」から、ECで注文された商品を迅速に消費者へ配送する「物流センター」へと進化しました。
これは物流拠点の主要機能が「様々な場所から届く商品を効率的に保管し、注文された商品をピッキングして1件ずつ梱包する」ものへ進化したことを意味しています。
従来の倉庫では商品をパレットに積み上げ、フォークリフトで収納する「パレット保管」が多用されていますが、物流センターではピッキングしやすいよう商品を箱ごとに分類して保管する「バラ保管」も主流になりました。
一方で、倉庫全体での保管スペースの拡大需要も増え、施設の上部空間を活かした高層ラックを導入する現場も増えてきました。
物流センターの「ピッキング効率と保管効率のジレンマ」
しかし、「バラ保管」と「高層ラック」を組み合わせた運用は、一つの問題を孕んでいます。
①高層ラックでのバラ保管はピッキング効率が悪い?
物流センターの出庫作業において商品が“箱ごと”必要になるケースは少なく、大抵の場合は箱の中から1つの商品をピッキングするだけです。
しかし手の届かない高層ラックの上層に置かれた箱から商品を1つ取り出そうとすると、以下のような手順が必要になります。
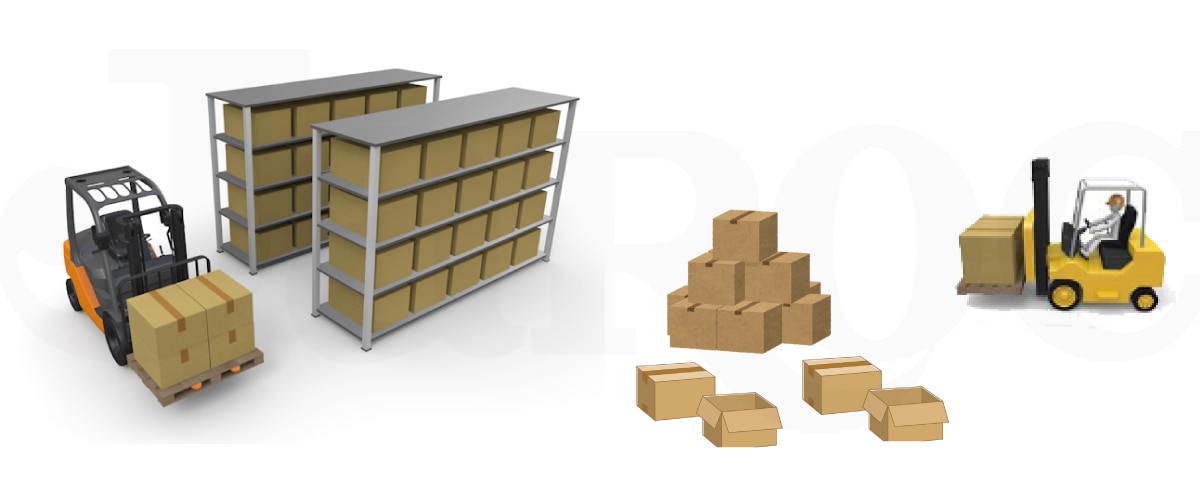
①フォークリフトで目的の箱がある場所まで移動
②フォークリフトで目的の箱を持ち上げ、地面まで降ろす
③箱を開けて商品を必要数ピッキングする
④箱をフォークリフトで持ち上げ、元の場所へ戻す
この運用を続けると、手の届く高さに置かれた箱からピッキングするよりも遥かに煩雑で時間がかかります。
また、フォークリフト免許を持つ従業員が必須となるためコスト面や人員確保面でも多くの課題があります。
逆にピッキング効率を優先して高層ラックを使用せず、手の届くエリアにしか商品を置かない場合、物流センター内に抱えられる商品点数は著しく減ってしまい保管効率が犠牲になってしまいます。
備蓄倉庫など、1回の入出庫量がパレット単位の現場なら問題ないのですが、そうではないバラ保管と高層ラックでの運用は相性が悪く、保管効率を重視すればピッキング効率が悪化し、ピッキング効率を重視すると保管効率が犠牲になるというジレンマを生むことになります。
高層ラック環境におけるピッキング効率改善方法
この「ピッキング効率と保管効率のジレンマ」を解消するため、業界では様々な試みが行われています。
頻度分析による入庫位置調整
商品が入庫した際、出荷頻度の高いものは手が届く低層の棚へ、低いものはフォークリフトが必要な高層の棚へそれぞれ入れることでフォークリフトを使ったピッキング回数を削減しようというアプローチです。
様々な事業者が提供しているピッキングシステムの中には、頻度分析をして入庫位置を指定してくれるものもあります。
ただし、このアプローチではフォークリフトによるピッキングをなくすことはできません。
脚立や梯子の利用
フォークリフトの代わりに脚立や梯子を使ってピッキングしている物流現場も多くあります。
ただし、このアプローチは作業者に脚立等を持って広い物流センターを歩き回らせることになり身体的負荷が重いだけでなく、不安定な足場でのピッキングをさせることで事故リスクも高いです。
高所作業車「ハイピックランナー®」の導入

専用の高所作業車で作業員を高層エリアへ送り込み、棚から箱を降ろさず直接商品をピッキングするアプローチです。
ジャロックの高所作業車「ハイピックランナー®」は操作方法も簡単で運転にフォークリフト免許が不要なため、パート・アルバイトの作業員でも高所ピッキングが可能です。
安全性も担保されているため事故のリスクも極めて少ないです。
また、幅80cmとコンパクトなため必要通路幅を最小1.1m程度まで圧縮して保管効率をさらに高めることもできます。
ハイピックランナーでピッキングする場合の操作手順
ハイピックランナー®と高層ラック運用の場合、手順としては以下になります。
①手元のハンドルを操作し、任意の高さまで昇降する
→ハイピックランナーの場合、5mの高さまで昇降できます。②人の手で直接商品をピッキングする
→取り出した商品は手前や背後のテーブルに置くことができます。③ハンドル操作で降下し、走行してラックを出る
→そのまま梱包エリアまで移動する事ができます。
これによりフォークによるパレットの上げ下ろし作業を削減し、人手不足にもケアしながら効率的なピッキングが可能になります。
自動倉庫
物流センター全体を自動倉庫化することで解決するアプローチもあります。
一部の自動倉庫では、シャトル型のロボットが高層ラックを昇降し、目的の商品が入った箱をピッキング担当者が待つエリアまで、次々と持ってきてくれるものが実用化されています。
ただし、自動倉庫の導入には相応の設備投資額が必要になります。
価格と安全面で考えれば「ハイピックランナー®」レンタルがおすすめ
保管効率とピッキング効率のジレンマを解消するアプローチとして、「商品取出時間の短縮」という切り口でいくつかのアプローチを見てきました。
ピッキング効率の改善には「商品取出時間の短縮」の他にも「商品を探す時間の短縮」や「商品棚までの移動時間短縮」といった切り口があり、これらも一体で考える必要がありますし、物流現場それぞれに置かれた状況(商品の種類や入出庫の頻度、物流センターの広さや所在地など)が異なるため、最適なソリューションは様々です。
また、価格やランニングコストの面でも考慮が必要です。
ジャロックではお客様目線で考えて「ハイピックランナー®」のレンタルプランをご提案するケースが多いです。その理由は主に以下の3つです。

メリット①初期費用が0円
「ハイピックランナー®」はレンタルで利用する場合、初期費用は0円です。
社内稟議を通して導入費用の予算を確保したり、金融機関から新規融資を受けたりする必要が無いため、価格の面で非常にお得な導入ができます。
また、ファイナンスリース契約等と違ってレンタル費用の全額を経費計上でき、固定資産税の対象にもならないため税制面でも有利です。
メリット②高い安全性
ハイピックランナー®走行中は前後にパトライトが点灯し落下防止対策も万全です。また、緊急時の手動下降装置を搭載しています。
「上昇した際の揺れもほとんど感じない」と褒めていただくことも多く、見た目の印象よりも遥かに昇降中の安定感は高いです。
ピッキング中も安定した足場を確保できるため脚立や梯子よりも事故リスクは低いといえます。
契約時に動産保険もつくため、万が一の事があっても安心です。
メリット③ラックと合わせてレンタルも可能
ジャロックでハイピックランナー®を導入する場合は、合わせて高層ラックのご提案をすることも可能です。
例えば、ジャロック独自のラック「タナTSumU®(タナツム)」は、ハイピックランナーとセットでのレンタルが可能です。
貸倉庫などで恒常的な運用が難しい現場でも容易に高層ラック運用が利用でき、効率的な保管とピッキングの両立が可能となります。
タナTSumU®との連携についてはコラムもぜひご覧ください。
まとめ

EC市場の拡大による物流センターの進化は、保管とピッキングの効率化ジレンマを生み出しました。しかし、ジャロックの「ハイピックランナー®」レンタルなどの解決策により、これらの課題は克服可能です。
まだ高層ラック化していないという物流現場でも、既存の棚の上部に新しい棚を設置する「タナTSumU®」というソリューションとの併用でピッキング効率を犠牲にせず保管効率を大幅に改善できますので併せてご検討いただきたいです。
まずは下のリンクから「ハイピックランナー®」のカタログをダウンロードしてみてください。
レンタルについては「タナTSumU®×ハイピックランナー®安心レンタル」パンフレットをご覧ください。
ジャロックはお客様の現場によってさまざまなソリューションをご提案していますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。